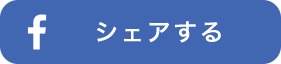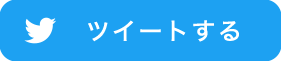-
![労働生産性について改めて考える!働き方改革の本質]() 2018年7月に「働き方改革」に関する法律が公布され、働き方の改革が国の重要政策として掲げられました。厚生労働省の『「働き方改革」の実現に向けて』では「投資やイノベーションによる生産性向上とともに、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境を作ることが重要な課題」であると、その指針を述べています。
2018年7月に「働き方改革」に関する法律が公布され、働き方の改革が国の重要政策として掲げられました。厚生労働省の『「働き方改革」の実現に向けて』では「投資やイノベーションによる生産性向上とともに、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境を作ることが重要な課題」であると、その指針を述べています。
INDEX
目的に立ち返る!働き方改革の本質
2018年7月に「働き方改革」に関する法律が公布され、働き方の改革が国の重要政策として掲げられました。厚生労働省の『「働き方改革」の実現に向けて』では「投資やイノベーションによる生産性向上とともに、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境を作ることが重要な課題」であると、その指針を述べています。
こうした状況の背景には、日本が抱える少子高齢化社会の存在があることは言うまでもありません。現実的には多くの企業が人手不足、過重な残業時間、外国人労働者の活用などの問題に直面しています。
働き方改革では眼前の問題に真摯に向き合いながら、対症療法的に逐一解決していくことも必要です。しかし最も大切なことは、働き方改革の根底に横たわる「生産性」と正面から向き合い、実際の生産性向上に結びつけることではないでしょうか。
つまり、個々の企業が企業実状に則しながら、具体的な生産性向上の対応策を練ることが働き方改革の本来の目的になるわけです。
定義をおさらい!労働生産性の計算方法
生産性のメインテーマは「労働生産性」です。労働生産性の向上は、働き方改革の中核をなす重要テーマなので、その定義をきっちり理解しましょう。
労働生産性には「物的労働生産性」と「付加価値労働生産性」の2種類あります。それぞれの定義を計算式で表すと次のようになります。
・「付加価値労働生産性」=「付加価値産出量」/「労働者数×時間=労働投入量」
前者の主眼は生み出された産出物の物的量にあり、後者の主眼は生み出された価値の量にあります。両者の最大の差は、前者が「商品をいかに多く生み出したか」であるのに対して、後者は「売れた商品をいかに多く生み出したか」にあります。
物的労働生産性は商品を作ればそのまま売れていく、工業化社会黎明期に最もよく適応した指標です。一方で、付加価値労働生産性は現在のように簡単には商品が売れない市場成熟期に適用されなければいけない指標です。物的労働生産性云々を働き方改革の入り口として取りかかると、大きな誤謬(ごびゅう)を招きかねません。
したがって、付加価値労働生産性に焦点を当てる必要があるわけです。つまり、商品が実際に売れたかどうか、労働自体が付加価値を生むものになっているのかどうか、が重要な論点になります。
日本の労働生産性が低い理由とは?
日本生産性本部2018年版の労働生産性国際比較によると、日本の時間当たりの労働生産性(就業1時間当たり付加価値)は47.5ドル(4,733円)でOECD加盟36国中20位、主要先進7カ国の中では最下位となっています。
また、日本の1人当たり労働生産性(就業者1人当たり付加価値)は、84,027ドル(837万円)、OECD加盟36カ国中21位となっており、ここ40年以上国際比較での労働生産性は継続的に低位を続けています。
つまり、1人あたりのGDPが相対的に低く、日本の付加価値労働生産性も他国と比べて低いことを意味しています。
日本の1人あたりGDPが低いのは、主にサービス業の付加価値労働生産性の低さと関係がありそうです。製造業の大企業は比較的付加価値労働生産性に貢献しているようですが、それでも実態としては過重な残業時間や低有給休暇取得率などによる歪(いびつ)な構造によって支えられていることは否めないでしょう。
サービス業ではサービスそのものが付加価値として適正にカウントされ、売上げに貢献しているかと言えば、必ずしもそういうではない実態があります。
結果として、低い付加価値労働生産性をこのまま放置していれば、売上げも利益も増えず、さらなる長時間労働を招き、人手不足で黒字倒産するなど、疲弊の悪循環を引き起こすことが予測できます。
生産性の向上に効く、単純作業の減らし方
付加価値労働生産性の計算式を別の書き方で記述すると、
となります。
※Va(Value-added:付加価値)、Mp(Man power:労働者数)、h(hour:時間)

厳密にいえば、Mp=標準労働力×労働者数で、通常標準労働力は1なので、Mp=労働者数となります。
さてこの方程式における数値は全て結果、あるいは前提条件として固定値で与えられますが、Mpは本来従業員個々人の能力差が出る変数であり、Mp全体は個々の従業員の能力の集積です。つまりMpは労働者数という単純な数値で認識すべき対象ではありません。
本稿では、この方程式中のMpに焦点を当てて論じてみたいと思います。先述の通りMpは実際には個々人の産出能力に関わる変数ですので、それをCMp(x)とし、VaLP=Va/(CMp(x)・h)で考えてみる、というのが今回の論点になります。CMp(x)は企業ごとの変数で、Mpを集積個人別能力で割った値になります。CとはCorrected(修正)の頭文字で、CMp(x)=Mp/(x1+x2+…xn)と示すことができ、修正労働投入量と称することができるでしょう。

結論を急げば、CMp(x)を労働生産性向上のために変動させる決め手は個々人の能力を増加させ、付加価値増加に必要な労働投入量を減らすこと、つまり計算式の分母値を小さくすることです。
例えば、3人分の産出量を1人でこなせれば、生産性は3倍になります。CMp(x)の中には商品の成功率やコンペでの勝利率なども含まれてくるでしょう。このCMp(x)を縮減させることで、結果付加価値労働生産性を増大させることができます。
そのための具体策としては、次の3つの方策が考えられます。
2. AI、ロボットなどのテクノロジーのサポートによる単純作業やルーチン業務の置き換え
3. 付加価値増加のための専門的特別スキル・アップ策の実施
当面の課題として、個々人の付加価値を生み出すための産出能力を具体的に高めながら、その集積としてのCMp(x)を減少方向にコントロールしていくことが重要です。
まとめ
日本の社会は急速に進む労働人口の減少に直面しています。各企業は事業を継続させるため働き方改革による対策が待ったなしの状況になっています。働き方改革を進めるにあたっては、その中核となる付加価値労働生産性を高めることが鍵です。そのためには付加価値労働生産性の明確な定義や意味の理解が肝要となります。
国際的に見て日本全体の付加価値創造が不足しているのは事実であり、その結果悪循環として過重な長時間労働や低有給休暇取得率などの疲弊を生み出している現状があります。
対応として個々の企業の実状に即した、新しくデザインされた付加価値労働生産性に関する方程式を用いながら、データに基づく具体的な方策を実施していくことが求められています。
CMp(x)という変数への挑戦が、テレワーク、残業ゼロ化、やりがい、給料体系の見直し、商品開発戦略や経営戦略の見直しなど、各種のサブテーマを展開させ、精神論を超えたロジカルな対策方法を浮かび上がらせてくるでしょう。
文責:山口 泰幸(経営コンサルタント・ブランドコンサルタント・概念デザイナー)
概念デザイン研空所 主宰
日産自動車(株)で車両実験、商品企画・開発・将来車両研究、先行デザインに従事し、同労組常任委員(人事・労務・経営協議等を担当)も経験 。1996年2月に概念デザイン研究所設立し、各種企業プロジェクトに参画している。2000年以降、複数の美大にて概念デザイン論の非常勤講師を兼務。 経営から商品・人材開発まで幅広く、概念デザイン・メソドロジーという独自の武器で、問題解決力の強化・習得をサポートしている。
関連記事
-
![働き方改革に効く!?「オフィス空間づくり」で生産性向上を目指す]() 2020.06.10
2020.06.10働き方改革に効く!?「オフィス空間づくり」で生産性向上を目指す
働き方改革というと、残業規制などが注目されがちですが、本質的には少子高齢化を背景に少人数でも日...
-
![生産性向上を実現して働き方改革実現を!取り組み策と注意点を解説]() 2021.04.13
2021.04.13生産性向上を実現して働き方改革実現を!取り組み策と注意点を解説
業務効率化やコストの削減など、生産性向上の必要性・重要性が指摘される場面が多々あります。しかし...
-
![業務効率化に効く4つのアイデア]() 2019.03.28
2019.03.28業務効率化に効く4つのアイデア
世の中のトレンドワードとして定着している「働き方改革」。働き方改革を自社の経営に対してプラスに...