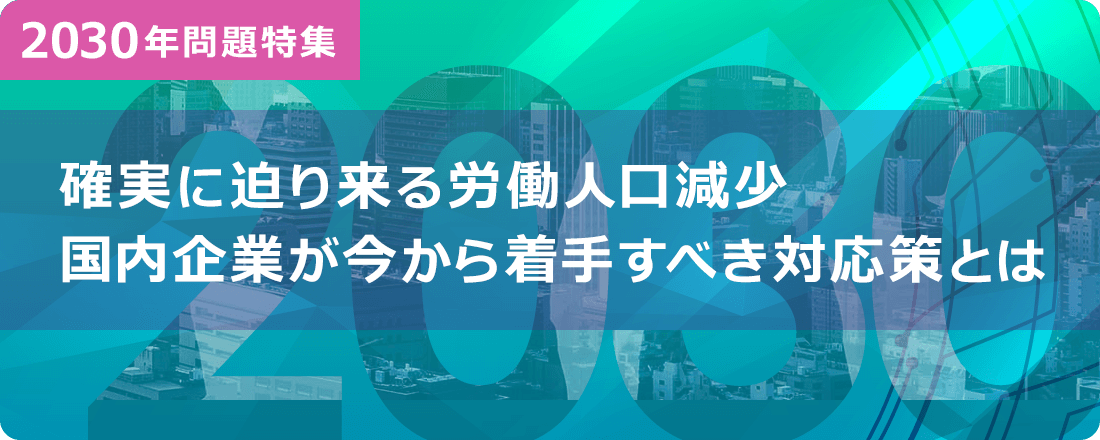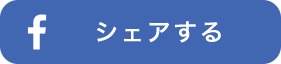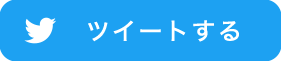INDEX
- そもそも「働きがい」とは?
- 日本企業もジョブ型を取り入れるべき?
- ジョブ型は離職率が増加しやすい?ジョブローテーションの意味
- 「働きがい」を向上させるには?解決の糸口
- 【問題4・5の核心】顕在需要を追い過ぎた結果のコモディティ化と価格競争
- まとめ
そもそも「働きがい」とは?
従業員目線での「働きがい」とは何なのかについて考える際には、少なくともその答えが一つではないことを理解しなくてはいけません。前回のコラムでは、「働きがい」を「その業務に従事することにより、従業員自身の現在や将来に対する魅力的な体験が得られること」と定義しました。ここでいう「魅力的」の指すものが人によってかなり違うのですが、単なる好みの問題というよりも、もっと大きな捉え方をする必要があります。そのためにまず、日本流の「働きがい」と欧米流のそれとでは全く異なるということを解説します。
欧米流の「働きがい」:欲求の頂点にあるのは「自己実現」
次の図は「マズローの5段階欲求モデル」です。

このモデルでは、自身の生命を維持するための生理的欲求を最下層に置き、下から順に満たされていくという捉え方です。そのなかでは3階層目から上の部分を「働きがい」の質の高さとして、以下のように読み替えられると思います。
・承認欲求:自分のアウトプット(仕事)の良さを評価され、認められるようになりたい
・自己実現欲求:自身の描く理想像を追い求め、自分にしかできない成果をあげたい
欧米流の働き方は、社会的欲求や承認欲求を満たした上で自己研鑽をし、成果を出すことで最上位にあたる自己実現欲求を満たすことが理想像になっているようです。というのも、欧米のサラリーマンは企業よりも職に属するという文化(ジョブ型)だからです。自らが身に付けた技能や専門知識を武器に、それを高く買ってくれる企業と契約をし、与えられたコンディションのなかで最高の成果を獲得するために挑戦しつつ、自身が考えるキャリア獲得のために適宜転職していくというスタイルが一般的です。
日本流の「働きがい」:社会への恩返し

多くの日本企業では雇用主と労働者との間の契約関係を正とし、企業に労働力を提供してその対価を得るという関係性が構築されています。こうした仕組みも欧米を規範としたものであり、日本でも一般的です。しかし、先に述べたように日本ではジョブに属する文化はあまり根付いておらず、新卒入社時からずっと同じ企業に勤める終身雇用の考え方(メンバーシップ型)が強く存在します。その理由は諸説あると思いますが、昔の日本社会に「仕事に就くことは社会への恩返し。そのために自身の役割を全うする」といった考え方が存在したことも一つだと思います。この「恩返し」という言葉にぴったり合う英訳は見つからないので、日本の文化ならではの感覚なのかもしれません。
日本企業もジョブ型を取り入れるべき?
では、「働きがい」を向上させるために、日本の企業はメンバーシップ型の働き方を見直したほうが良いのでしょうか?「メンバーシップ型」によってどのような効果を得られたのか、過去の出来事を振り返ってみましょう。
昭和の時代、日本のGDPはアメリカに届くかという勢いで急成長し、家電製品や自動車における世界の最先端が日本製品であるという状態が存在しました。その名残で「日本の技術を使わなければ製品を作れない」という分野が今も数多く存在します。メンバーシップ型で働く日本のサラリーマンが、ほかの国には作れない洗練された商品をいくつも出して世界シェアを獲得してきました。
また、全世界でも長寿の企業は日本が断トツに多いことも挙げられます。日経BPコンサルティングの調査によると、全世界にある創業200年以上の企業のうち、6割以上が日本企業だということも分かっています。第4話で触れたように日本国内の企業数は減っている一方で、老舗企業が残っているのもまた事実なのです。 明治・大正時代やなかにはそれよりも遥か昔から、厳しい環境を乗り越え、経営者も従業員も何代にもわたって世代交代をしながら事業を継続し、今なお消費者から支持されている企業もあります。
今の時代、企業によって働き方は様々ですが、かつては「メンバーシップ型」を取り入れて成長を実現してきた日本企業はたくさん存在します。このように考えると、一概に「メンバーシップ型」を見直すことが正しいとは言えないのではないでしょうか。
ジョブ型は離職率が増加しやすい?ジョブローテーションの意味

このように働きがいの観点から考察していくと、欧米流では職に属し、日本流では企業に属するという、就業に対する捉え方の違いに帰着します。
もし、今後の採用活動を仕掛ける際に欧米で主流の「ジョブ型」、すなわち求める職能と期待する役割を明確に定義し、その人に活躍できるフィールドと成果評価基準を明示するようなスタイルを取れば、そこにぴったりはまる就職活動者が応募をしてくるでしょう。
しかし、その人に期待したプロジェクトを成し遂げたあと、いかに社内のメンバーとの良好な人脈が形成できたとしても、繋ぎ止めておくことはできません。「人材は流動的である」という前提のもと、自社も次の成長戦略とテーマを設定し続け、次の新たな求人をする必要があります。
ですが、「そう言われても、なかなか自社でそのイメージを描くのは難しい」という国内企業がほとんどではないでしょうか。日本流の「メンバーシップ型」のもと、人材採用と育成のスタイルについて観察してみましょう。
例えば開発で入社した人が生産や企画に異動になり、最終的に人事や総務のリーダーとなるような「ジョブローテーション」が行われている企業が少なからずあります。日本流の企業でも、採用時は欧米流で言うところの「ジョブ」にあたる職能(例えば大学卒であれば「学士」という資格にあたる)で人材獲得をしているように見えるのですが、その人材の職能を発揮できる場が入社時に与えられた仕事のまま生涯変わらないとは限らず、いつかどこかで異動を経験することになります。そのようななかで、「最初はためらっていた部門に異動してみたら案外楽しかった」、「以前より働きがいを感じるようになった」という経験談も多いことでしょう。
ですが、ジョブローテーションが活発に行われる企業であっても、人事部門や経営層は、従業員全員のキャリアプランを設計しそのとおりに履行することは難しいと考えます。多くの人材はその場その場の必然性により、キャリアの観点では偶発的な異動を重ねることになります。そうなると、様々な部門で蓄積されていく経験値が社外(社会や業界)でそのまま通用する「専門性」へと成長させることは難しいかもしれません。
ここで重要なのは、偶発的な異動文化自体が社員の「働きがい」を失わせているわけではないということです。異動の過程で自分固有のキャリアが形成され、その時々のジョブに応じて多様なセンスを身に付け成長していく機会。これを多くの人材が経験できる日本企業の仕組みは、欧米流の企業では真似できない固有の強みでもあります。上手く活用すれば、無理にジョブ型を取り入れなくても、メンバーシップ型の強みを活かし、競争力の高い人材育成と離職率の低減とを両立させることができると考えます。
「働きがい」を向上させるには?解決の糸口
「働きがい」の理想像に多様性がある一方で、「働きがいが見いだせない」という状況は比較的シンプルに考えることができると思います。考えやすい実例としては、特定の企業よりも、直近の日本でのコロナ禍対応がもっとも顕著で適しています。
2020年春から始まったコロナ禍の状況を一言で表すと、「2週間先のことが見えない3年間」ではないでしょうか。例えば以下のような事柄を挙げられます。直近のことだけでなく、コロナ禍が始まった頃からを一度思い返してみてください。
・いつの間にか前提条件がどんどん変わっており、守るべきルールなどもどんどん変わるが、どんな結果を元に変えられたのかが把握しにくい
・疑問に思うことがあってもそれを解消するための情報が得にくく、事象を繰り返すごとに有益な気付きや学びの機会が減る(マンネリ感)
コロナ禍の対応は誰もがはじめての経験で、予測が難しい状況で試行錯誤して推進されているため、一概に施策の否定はできません。ですが、もしこれらの要素が企業内での定常業務やプロジェクトの進め方に重なる部分があったらどうでしょうか?おそらく「働きがい」を感じにくいのではないかと思います。上記のような要素から転じて、「働きがい」をつくるためには下記のような要素が必要と考えられます。
・未知の事柄への挑戦により何らかの結果が得られ、それを次回の挑戦への学びと軌道修正に活かすことができる
・担当者の気付きや学びは共有や洗練によって他のメンバーや上位層の共通認識の形成に繋がる
・それらを通じて、自身や組織の成長を常に感じることができる
これらを実現するには、①個々の従業員に挑戦すべきテーマがあり、②その達成のために創意工夫や試行錯誤をする余地があり、③その挑戦と結果が尊重される風土があることが必要だと考えます。個々の従業員に様々な考えやスキルがありますから、挑戦すべきテーマは大きくても小さくても構いません。従業員各自が自分で「挑戦してみたい」「頑張ってみたい」と思えるテーマを設定して挙げることが、長期的な「働きがい」をつくるきっかけにつながるのではないかと考えます。
【問題4・5の核心】顕在需要を追い過ぎた結果のコモディティ化と価格競争

最後は、「賃金上昇と商品の値上げ」と「国内需要の減少に伴う販売量の低迷」ついての考察です。これらが起こる背景として、市場拡大期の時に陥ってしまいがちな顕在需要を追い求める企業間競争があると考えます。経営者もしくはそれに近い方々にとってはよく聞く話かもしれません。
実際問題、一度この競争モデルに陥ってしまうと、なかなか抜け出すことはできません。製造業の場合、コストと効率化を追求すると、企画から開発、生産、販売までのプロセス全体が現状維持の観点で最適化されるため、同じ事業を継続しながらこれを崩して作り直すことは極めて難しくなるでしょう。 「最上流の企画の責任が一番重い」と思う方も多いかもしれませんが、その企画がいくらマーケティングを頑張って斬新な商品を考えたところで、自社の開発や生産が対応できなかったら絵に描いた餅になり、結局はコンサバな商品企画に落ち着きます。
また、競合企業とのシェア争いも落ち着き、一見安定しているように見える場合でも、第1話で紹介したプラットフォーマーのような新規参入企業が新しい競争軸を持ち込んできたら、同業他社もろとも根こそぎ市場を持っていかれるのではないかという漠然とした不安は拭えないでしょう。さらにはそれが唐突に起きなくとも、国内の需要は刻一刻と縮小していくのです。「生産性を向上させる」ことが命題となった国内企業においては、ここが一番の悩みではないでしょうか。
ここで視点を変えて、「生産性」という突破口について考え直してみます。例えば今皆様ご自身が組織のマネージャーだったとして、部下の生産性を1.5倍にするような業務指示が出せるでしょうか?おそらく指示できるのは残業時間の削減など、業務の「量」だけではないかと思います。「生産性」というのは、同じ労働量でアウトプットする成果(端的に言うと売上や利益)のことです。もし、指示一つで商品の売価や客単価が1.5倍に上がるのなら、とっくに実行できているはずです。経営者からのトップダウンの指示では効率化やコストダウンは進められても、生産性向上は難しいのです。
ですが、それは「生産性はもうこれ以上は上げられない」という意味ではありません。生産性を上げるための鍵はマネージャーだけでなく、実務と向き合うメンバーがたくさん握っているということです。
例えば、実際にお客様と対面している営業がお客様の悩みをもっと深く知り、本質的な課題を解決するような商品を提案できたらどうでしょうか。あるいは日々の業務手順に無駄な工程があることを見抜き、簡略化と同時に業務品質を向上させるような新しい手順を発案できたらどうでしょう。それらは担当者が目と手と頭を使い、担当者同士やお客様との対話を重ね、それらを通じた試行錯誤によって生まれ得るものです。そして、これは既存事業であっても実行可能なことでしょう。
「枯れた雑巾を絞る」という言葉がありますが、長く勤めている社員から見るとカラカラに乾いている業務でも、ほかから来た人にはびっしょり濡れて見えることがあります。これは転職者だけでなくジョブローテーション者も同様です。それは効率化の度合いではなく、目の付け所が違うのです。お客様や次工程の価値・体験を考え、「より良いものを受け取ってもらえるようにするにはどうしたら良いのか?」という思考回路で、自らの業務や成果物に対する創意工夫をし続けることがもっとも大切で、そのためには観察眼の視点をたくさん持つことが必要です。自社の良いところや改善点を多方面から見抜くために、様々な工夫ができるでしょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。従業員目線の「働きがい」と企業の「生産性」は別モノのように見えて、実はとても関係があることをご理解いただけたかと思います。次回はこれらを踏まえた解決アプローチのご提案として、コニカミノルタジャパンがなぜ「いいじかん設計」を提唱しているのか、その背景にも迫っていきたいと思います。
働き方に関する最新の取り組み情報をお届け!
最新コラムの更新もお知らせします。
いいじかん設計 編集部
関連記事
-
![#4 企業間の生存競争はもう始まっている!明るい未来は誰が描ける?]() 2022.12.01
2022.12.01#4 企業間の生存競争はもう始まっている!明るい未来は誰が描ける?
これまでの記事は日本の労働人口の減少に加え、平均所得の停滞や国内の消費人口の減少によるマーケットの縮小...
-
![#5 効率化の追求よりも、従業員の知識と特性を引き出す仕掛けが大切]() 2022.12.08
2022.12.08#5 効率化の追求よりも、従業員の知識と特性を引き出す仕掛けが大切
前回は、人口が減っていく過程で、国内に流通する商品が減少してシンプルなマーケットになっていくと同時に...
-
![2030年問題で労働人口はどう変わる?企業にできる備えとは]() 2021.06.24
2021.06.242030年問題で労働人口はどう変わる?企業にできる備えとは
2019年末から新型コロナウイルス感染症の拡大により、世界は大きな混乱をきたしています。いまだ...