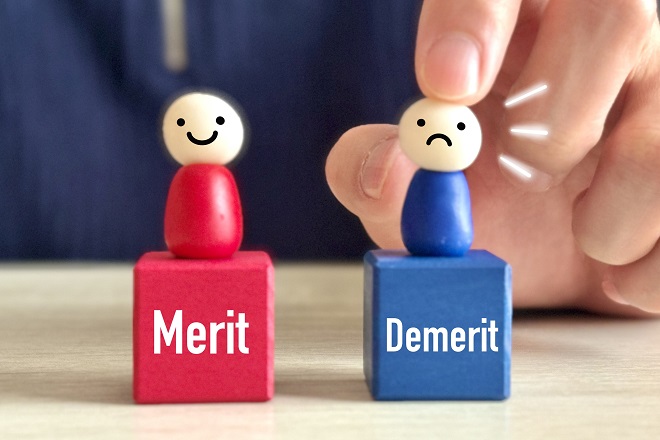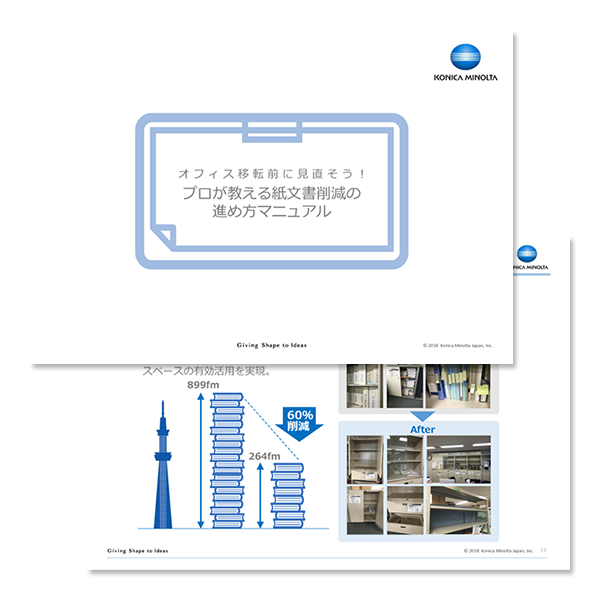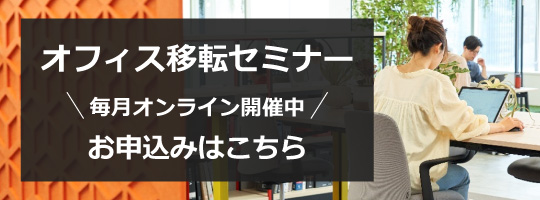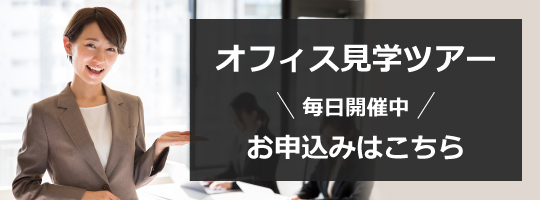プロが教える!紙文書削減の進め方のコツ
オフィスに紙があふれスペースがなく、捨てたいのだけど何から手を付けたらよいかわからない。そんなお悩みにこの1冊。紙削減のやり方から効果測定までプロの技をお伝えします。
ペーパーレスとは、紙を使わず日常業務を行うことをいいます。従来、事務作業で使用していた紙をデータ化し、環境保全を推進しつつ業務効率化も実現することを目的とした取り組みがペーパーレス化です。
今回は、ペーパーレス化を推進する際に注意すべきデメリットや、デメリットを解消するための考え方について解説します。ペーパーレス化への取り組みを検討されている事業者様は、ぜひ参考にしてください。
ペーパーレス化によって生じる主なデメリット
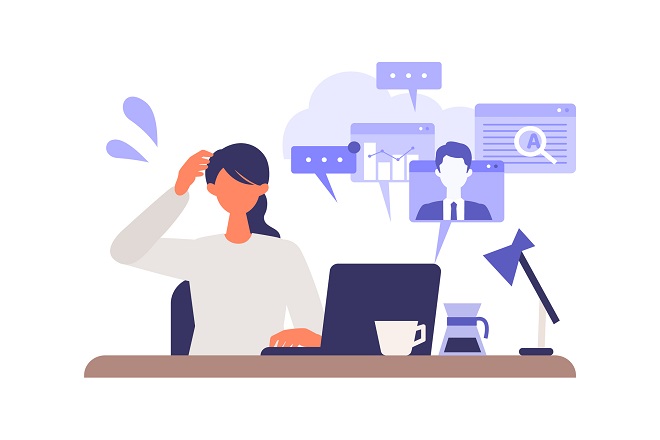
ペーパーレス化を推進することによって生じるデメリットとして、以下の5点が挙げられます。
・視認性・一覧性が下がる
・メモの書き込みがしにくい
・システム障害などの影響を受ける
・システム導入コストがかかる
・書類によっては紙で保存する必要がある
それぞれ詳しく見ていきましょう。
視認性・一覧性が下がる
ペーパーレス化のデメリットとして挙げられるのが、読みやすさが低下する場合があるという点です。とくに大判の書類であれば、書類全体を閲覧する際にパソコンやタブレットの画面上をスクロールして確認しなくてはなりません。視認性や一覧性に関しては、デジタルデータよりも紙のほうが優れている点も多々あるのは事実です。
こうした課題を改善するためには、データで閲覧することを前提に書類を作成することが重要です。パソコンやタブレットで表示することを想定した「用紙サイズ」「文字サイズ」で制作をすることにより、デジタルデータ特有のデメリットを解消できます。
メモの書き込みがしにくい
紙媒体のようにペンで直接書類に書き込めないこともデメリットとして挙げられます。情報を書き込みたい場合、都度パソコンやタブレットを立ち上げる必要がある上に、文字をキーボードで入力しなくてはなりません。
こうした一連の操作に慣れていない従業員にとって、紙のほうが利便性の面で優れていると感じるのは自然なことです。書類によってはメモが取れないことで利便性が著しく低下しかねないため、ペーパーレス化を推進するにあたって課題の1つとなるでしょう。
システム障害などの影響を受ける
ペーパーレス化のデメリットとして挙がりやすい問題の1つがシステム障害です。データのバックアップを取っておいたとしても、社内で保管していたデータが何かの原因で消えてしまう可能性はゼロではありません。一時的な通信障害やクラウドサーバー障害などの影響により、業務に必要な書類を閲覧できない状態に陥ることもあり得ます。
システム障害は起こり得るものと捉え、データのバックアップを習慣化していくことが大切です。バックアップを自動化したり、保存されたデータを管理する方法を検討したりする必要に迫られることは、ペーパーレス化を推進する上で直面するデメリットの1つといえるでしょう。
システム導入コストがかかる
ペーパーレス化に向けたシステムの導入に際して、次のようなコストを考慮する必要があります。
・従業員に貸与するパソコンやタブレットの購入費
・堅牢なデータ管理体制の構築
・システムの導入に向けた従業員への講習・研修
既存のシステムとの入れ替えに要する費用もコスト面での負担となります。従業員数や企業規模によって変動する可能性があるため、システム導入時には見積もりを取るなどして、発注先を慎重に選ぶようにしましょう。
書類によっては紙で保存する必要がある
ペーパーレス化を導入すればすべての書類をデータ化できるとは限りません。ペーパーレス化できない書類の例として、次のものが挙げられます。
・任意後見契約書
・事業用定期借地権設定のための契約書
これに対し、一般的な契約書であれば電子印鑑や電子署名を利用することにより、契約締結や保存をクラウド上で完結できます。ただし、重要文書をデータ保存する際には「e-文書法(電子文書法)」や「電子帳簿取引法」といった法令を遵守する必要がある点に注意してください。
ペーパーレス化のデメリットを解消するための対策

ペーパーレス化のデメリットを改善するための対策方法は、以下の6点です。
・デジタルデータを前提に書類を作成する
・タッチペンが使用可能なデバイスに切り替える
・データのバックアップを取る
・ペーパーレス化の費用対効果を試算する
・書類ごとの保存ルールを確認する
・必要に応じて紙を活用する
それぞれ詳しく解説します。
デジタルデータを前提に書類を作成する
前述のとおり、デジタルデータを前提に書類を作成することにより、ペーパーレス導入以降の書類の見にくさなどを改善できます。紙に印刷するための書類作成から脱却し、デジタルデータを活用した業務遂行を習慣化していく必要があるでしょう。
たとえば、タブレット端末の画面サイズで書類全体を閲覧するには、B4やA3といった大判の用紙設定は適していません。社内文書の用紙サイズをA4で統一することをおすすめします。また、使用するフォントサイズの最小値を決めておくことや、画面を横スクロールしなければ確認できないレイアウトにしないことなど、社内ルールを決めておくことが大切です。
タッチペンが使用可能なデバイスに切り替える
紙であれば直接メモを書き込めますが、デジタルデータにはメモを書き込めないと思われがちです。タブレット端末やタッチスクリーン搭載のパソコンは、タッチペンによる手書き入力に対応しています。手書きへのニーズが高いようなら、タッチペンが使用可能なデバイスに切り替えるのも1つの方法です。
タッチペンによる手書きであれば、一度書いたメモを消去したり、書き直したりする操作も簡単にできます。また、1つの書類を複数名で共有し、同時にメモを書き込むこともできるため、共同作業がしやすくなるケースも少なくありません。このように、紙にはないデジタルデータ特有のメリット面を活かしていくことが大切です。
データのバックアップを取る
データを適切に管理するためのバックアップの方法は多岐にわたります。比較的安全といわれるバックアップの方法には「3-2-1バックアップルール」というものがあります。
【3-2-1バックアップルール】
1. データはコピーして3つ保有する
2. 2種類以上の機器にデータを保存する
3. バックアップの1つは遠隔地で保存する
何らかの障害が発生した場合に備えて、常にバックアップデータから復旧できるようにしておくことが大切です。近年は企業などの組織がランサムウェア攻撃の標的にされる事例も増えています。ランサムウェア攻撃を受けた場合、保存されていたデータが不正に暗号化されてしまい、使用できない状態に陥ることにもなりかねません。バックアップデータがあれば、攻撃者による脅迫や金銭の要求に応じる必然性がなくなるため、落ち着いて対処できるというメリットもあります。
ペーパーレス化の費用対効果を試算する
ペーパーレスのシステムを導入する場合、どれだけのコストが発生するのか、メリットがあるのかを試算してから導入しましょう。初期費用が安価でも、ランニングコストがかさむことで長期的には多くの費用がかかってしまうこともあります。
一方で、ペーパーレス化によってコスト削減が実現する側面もあります。一例として、次のような費用はペーパーレス化によって削減可能です。
・用紙代
・プリンターのインク/トナー代
・郵送代
・資料類の印刷・配布に要していた人件費
・必要な書類を探す工数
・書類のやり取り(送付/受取)にかかる工数
このように、ペーパーレス化によって一時的・継続的にかかる費用と、ペーパーレス化が実現することで得られる節減効果のバランスを考慮して費用対効果を試算しておくことが大切です。
書類ごとの保存ルールを確認する
書類ごとの保存ルールを確認しておくことも重要なポイントの1つです。とくに電子帳簿保存法への対応には注意してください。
電子帳簿保存法では、一貫して電子的に作成された書類はデータ保存することが義務づけられています。紙に印刷してファイリングするといった、従来の保存方法は認められていません。自社で発行した書類だけでなく、取引先から受領した書類についても、電子データとして授受したものに関してはデータのまま保存する必要があります。また、見積書・契約書・請求書・領収書といった書類は、紙で受領したものを所定の方法でスキャナ保存しても差し支えありません。紙とデータの書類が混在することで管理が煩雑になるようなら、ペーパーレス化を機にすべての書類をデータ化して一元管理するのも1つの考え方です。
必要に応じて紙を活用する
ペーパーレスに移行するからといって、あらゆる書類を一斉に電子化しなくてはならないわけではありません。必要に応じて紙を活用する考え方を柔軟に取り入れることで、ペーパーレス化のデメリット面を和らげる効果が期待できます。
たとえば紙のほうが便利であれば従来どおり紙を使い、活用後に紙をデータ化して原本を破棄するのか、もしくは原本を保存しておくのか判断しても構いません。無駄な紙を溜めない「ストックレス」という考え方にもとづいて運用していくことにより、ペーパーレス化を無理なく進めやすくなるでしょう。コニカミノルタジャパンでは、ペーパーレスとあわせてペーパーストックレスの考え方にもとづく運用についてもサポートしています。自社に合った運用方法を探している事業者様は、ぜひコニカミノルタジャパンにご相談ください 。
- 1
- 2