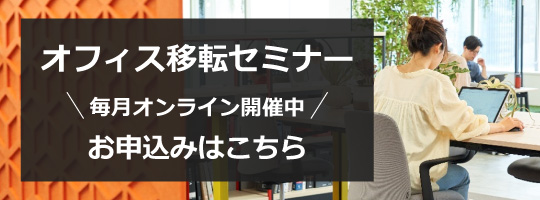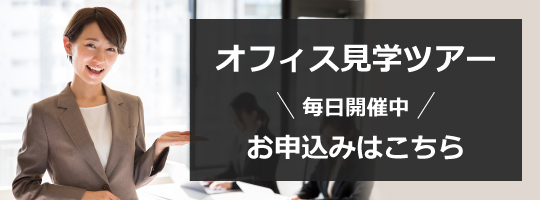フリーアドレスの目的から導入手順のほか、“全員でのフリーアドレスは難しい” という場合の選択肢、導入後の課題と解決策までまるっとご紹介!オフィス改善のヒントに、ぜひご覧ください。
オフィスをフリーアドレスに変更すべきか、変更した場合にどのようなメリットがあるのか悩んでいませんか? フリーアドレスには多くのメリットがある反面、フリーアドレスに適している企業と適さない企業があるのも事実です。
今回は、フリーアドレスのメリットや失敗例、代表的なレイアウト例についてわかりやすく解説します。フリーアドレスの導入手順や成功させるためのポイントも紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
目次
フリーアドレスとは

フリーアドレスとは、固定席を設けず空いている好きな座席を選んで仕事をするワークスタイルのことです。はじめに、フリーアドレスの種類や導入するメリット・注意点について基本を押さえておきましょう。
フリーアドレスの種類
フリーアドレスには大きく分けて「完全フリーアドレス」と「グループアドレス」の2種類があります。完全フリーアドレスとは、オフィス内のすべての座席を自由席にすることです。部署や部門を問わず、各々が好きな席で業務を進める点に特徴があります。
一方、グループアドレスとは部門や職種などのグループ内で座席を自由にすることを指します。完全フリーアドレスと比べると自由度は下がるものの、グループ内でのコミュニケーションを活性化させる効果が期待できるでしょう。
フリーアドレスを導入するメリット
フリーアドレスを導入する主なメリットは下記の4点です。
スペースの有効利用
自由席であれば、オフィスのすみずみまでワークスペースとして活用できます。固定席で発生しがちなデッドスペースを効果的に活用することにより、機能的で無駄のないオフィスレイアウトを実現しやすくなる点がメリットです。
コスト削減
オフィスを固定席から自由席にすることで、座席数の削減につながります。オフィスのスペースを有効活用しやすくなるため、オフィス面積のコンパクト化も実現可能です。さらにテレワークとセットで導入することにより、全員分の座席を確保する必要もなくなります。オフィスの賃料を抑え、固定費を削減できる点が大きなメリットです。
コミュニケーション促進
全員が毎日異なる席に座って業務に取り組むことで、部門や担当業務を越境したコミュニケーションが生まれやすくなります。従業員間の意思疎通がスムーズになったり、偶発的なアイデアが創出されやすくなったりする効果が期待できるでしょう。
レイアウト変更が容易
フリーアドレスではそもそも固定席を設けないため、レイアウト変更の自由度が高まります。増員に伴う座席の追加などにも対応しやすく、柔軟なレイアウト変更が可能となることはメリットの1つです。
フリーアドレス導入時の陥りがちな失敗例と対処法
フリーアドレスには多くのメリットがある一方で、注意が必要な点もあります。フリーアドレスで陥りがたいな失敗例と対処法について見ていきましょう。
常に同じ席に座るメンバーが現れる場合がある
フリーアドレスであるにもかかわらず、従業員がいつも同じ席に座ってしまうようでは本末転倒です。業務改善が見られない、他部署との連携が取れないなど、導入する意味がほとんど得られなくなります。フリーアドレスを導入する際、目的をしっかりと伝えましょう。さらに、上司や役職者から率先的に違う席に座るなどの取り組みを行うことも重要です。
座席を移動しても同じメンバーで固まりがち
座席自体は動いていても、いつも同じメンバーで固まってしまうという問題も起こりえます。デスクの配置をあえて互い違いにすることで、デスクの近くを通る際に自然にコミュニケーションが生まれる配置にするのは効果的な対策の1つです。

また、部署ごとにフロアや部屋を分けないようにしたりパーテーションを取り払ったりするなど、物理的な壁を取り払うのも有効な対策となるでしょう。近年の傾向として、分散した複数のフロアから1フロアのメガオフィスに移転する企業も増えています。
部署内でのコミュニケーションが低下する
他部署とのコミュニケーションを意識しすぎるあまり、部署内でのコミュニケーションが低下してしまうこともあります。あるいは、直接口頭で伝えていた内容がチャットツールに置き換わってしまう場合もあるでしょう。
朝礼や週ごとのミーティングなど定期的なミーティングの場を設けて、些細なことでも共有しあえる場を設けるのは効果的な対処法といえます。また、あえて完全フリーではなくグループフリーにするのも1つの方法です。東和エンジニアリング様のオフィスでは、完全フリーアドレス化後の従業員アンケートで、「他部署とのコミュニケーションは高まったものの、部内のコミュニケーションが希薄になってしまった」という結果が出ました。この意見に対する改善策として、「週に1度はグループフリーアドレスにする」という運用改善を実施されています。グループフリーでの実例のように、従業員の声に耳を傾けながら、それぞれの職場環境に合う環境を整えていく姿勢が重要です。
▶(イベントレポ)11月19日 東和エンジニアリング様の新オフィスでオフィス移転セミナー特別編が開催されました!
業務効率の低下につながる
パーテーションの垣根をなくし、人が絶えず移動する職場環境においては、業務効率が低下してしまうリスクも想定されます。個別のブースなど、集中して作業に取り組めるスペースを設けることは効果的な対策といえるでしょう。また、「この時間は一人で集中して作業をする」など、メリハリを意識したスケジュール管理を行う方法も有効です。
フリーアドレスに適している企業の特徴

フリーアドレスはあらゆる事業スタイルの企業に適しているとは限りません。フリーアドレス向きの企業の特徴として、次の5点が挙げられます。
ITツールで情報を一元管理できている企業
現状、すでにITツールを活用して社内の情報を一元管理できている企業は、フリーアドレスにスムーズに移行できる可能性が高いといえます。自由席になると、どの席からでも必要な情報を閲覧・更新できる仕組みを整えなければなりません。紙媒体で情報を管理している企業や、ITを使用していても個別のPCやハードウェアに依存している状況では、フリーアドレスを導入しにくい状況といえるでしょう。
紙にしばられない働き方を実践している企業
電子署名やワークフローシステムといったITツールを活用し、ペーパーレスを実現している企業はフリーアドレス向きといえます。書類への押印や稟議承認といった一連のプロセスが電子化されていれば、座席の場所にとらわれないフリーアドレスに移行しても支障ないからです。
フリーアドレスに合わせた意識改革ができている企業
フリーアドレスの効果やメリット面について、従業員が十分に理解している企業は、固定席を廃止しても大きな問題が起こりにくいでしょう。フリーアドレス導入によって生産性を高めるには、社内のどこで働いても成果が上がる状態にする必要がある、といった意識改革が求められます。
たとえば、近くに部下の席がないと管理が難しいと考えるマネジメントでは、フリーアドレス導入による十分な成果は期待できないでしょう。とくに管理職向けに研修を行い、部下が目の届かない場所にいてもコミュニケーションや評価ができるように意識を改革しておくことが重要です。
在席率が低く、在席時間にバラつきがある企業
すでにテレワークやフレックス制の導入済みの企業は、フリーアドレスとの親和性が高いと考えられます。フリーアドレスの大きな効果の1つは、限られたスペースを最大限に有効利用することです。スタッフの多数が同時に在籍することの多い企業や開発・研究部門などでは固定席になりやすく、フリーアドレスのメリットが得られない場合があります。営業時間を総合すると在席率は低くても、営業スタッフが定時に一斉帰社するような場合も、人数分のデスクが必要となるためフリーアドレスのメリットが生かされません。
確かなコンセプトを掲げている企業
フリーアドレス導入がしっかりとしたコンセプトに支えられている企業では、フリーアドレスのメリットが生かされやすい傾向があります。フリーアドレス導入の目的や意図をしっかりともった上で従業員に共有しなければ、フリーアドレスは形式的なものになりかねません。生産性の向上やコミュニケーションの活性化など、フリーアドレス導入による効果をコンセプトとして打ち出していくのが望ましいでしょう。