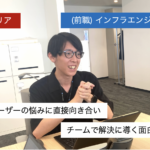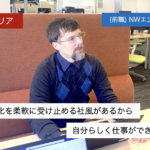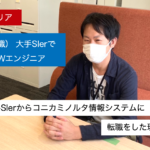ユーザーの本音が引き出せるから、喜ばれる提案ができる
2025.4.17

コニカミノルタ情報システムで働いている社員にスポットを当て、社員のリアルな想いを届ける「コニカミノルタ情報システムの“ヒト”」。今回は、キャリア入社として2021年に入社されたIさんです。(インタビューは2025年4月の情報です)
・ITサービス本部 基盤技術部 NSG(ネットワークセキュリティグループ)
・東京学芸大学 教育学部 出身
・前職:ユーザー系SIer企業にて、ネットワークインフラの保守・運用
・2021年度入社
長期的な視点でインフラの運用・改善に取り組める環境を求めて
ー転職を決意したきっかけを教えてください。
以前は、地元である長野県のSIerに勤めていました。3年半ほどネットワークをメインにインフラの保守・運用を担当し、小規模な案件では構築まで担うような業務内容でした。
転職を決意したのは、これからのキャリアを考えた時に自分の専門性をもっと深めたいと考えたからです。前職は中小規模の会社で、ネットワークエンジニアとして入社したのですが、監視オペレーターから電源ファシリティの管理まで業務の範囲が広く、だんだん自分の強みや専門性が何なのかを見失いそうになっていった感じです。
そこで、ネットワークインフラの運用や改善において、もう少し掘り下げて専門的に学びつつ、よりスケール感の大きな環境で自分の力を試したいと思い、転職を決めました。
ー最終的にコニカミノルタ情報システムを選んだ理由は何でしたか。
転職先を選ぶにあたっては、長期的な視点でインフラの運用・改善に取り組めることを重視し、特定のネットワーク・インフラ環境に安定的に関わり、インハウスSEとして専門性を高められる企業を中心に検討していました。
コニカミノルタ情報システムは、コニカミノルタのグループ会社全体のSEとして、継続的な改善に取り組める環境で、インフラの最適化に貢献できる点に惹かれ、入社を志望しました。
ー継続的な改善に取り組めるのは、内販100%だからこそできる強みでもありますね。
そうですね。内販比率100%という点も入社動機になった大きな理由です。前職の企業は、内販だけでなく、グループ外へのITサービスも提供しており、外販と内販の比率が半分ずつという環境でした。もちろん外部の取引先との仕事も張り合いがありましたが、顧客のネットワーク環境を深く理解し、運用改善を提案できる内販業務で得られるやりがいが、自分にとってはより魅力的でした。
というのも、一概には言えませんが、外販の場合ですと、例えば機器のリプレース案件に際して、設計・構築・導入フェーズを経て、安定した稼働が確認できれば基本的に完了となり、後はトラブル時のスポット対応という形になりますよね。当たり前ではあるのですが、ビジネスライクというかドライというか…作って終わりという傾向がどうしても強いように感じていたんです。
一方で内販はグループ内での仕事が基本ですから、導入して終わりではなく、継続的な保守・運用だったり、運用に対する課題を軽減したり、より良いものを作っていったり…自分が作ったシステムを最後まで見守り、寄り添うことができるところに強く魅力を覚えました。
ー特定のフェーズだけ対応するのではなく、要件に対して適切な構築をして、最後まで伴走してユーザーが使える状態に持っていく…そういうエンジニアのあり方がIさんには合っていたんですね。
成果を実感できるやりがいと、未知の分野に触れる楽しさ
ー今はどんな仕事をされているのですか?
コニカミノルタ本体およびグループ会社のユーザーに対して、ネットワーク・サーバインフラの保守・運用を担当しています。主には全社DNSサーバー、SMTP中継サーバー、リモートアクセスシステムを管理する他、老朽化したネットワーク機材やサーバーのリプレース対応も行っています。
グループ全体のネットワーク施策や戦略に関わるような案件ですと、IT企画部とコミュニケーションを取って進めていきますし、地方拠点のグループ会社から「新しくネットワークを設置したい」「老朽化したネットワーク機器の更新をしたい」といったケースでは、現地に赴いてユーザーと直接やりとりしてネットワークの設計や構築を進めていくような形です。
ー実際に入社してみて、どんなところにやりがいを感じていますか?
やはりユーザーと対話し、上流から運用までしっかり伴走できるからこそ、自分が設定・構築したサーバーやネットワークが稼働し、役立っていることを肌で感じられることが大きなやりがいですね。フェーズ毎に区切られる体制ですと“作っておしまい”になるので、どうしてもパラメーターシートや機器のコンソールなどと睨めっこする時間の方が多くなりがちです。やはり、安定した運用までを見届けてこそ私たちの仕事の真価ですし、顔を突き合わせて感謝の声を聴ける喜びも得られます。
ー予算や工数など表面的なところが重視され、本当にユーザーのためになっているかが置き去りに…みたいなケースもありますもんね。ただ、ユーザーにとことん向き合うためには、上流から運用までカバー範囲も広く求められるので、大変ではないですか?
広い知識が求められる部分は確かに苦労がありますが、コニカミノルタ情報システムが担っている運用や保守を通して、構築や設計段階における今まで知り得なかった細かいシステムの仕様を知れることは、やりがいにもなっているんですよね。動作試験表の通りに動いたので確認完了、ではなくて、「周辺システムと接続したところでこんな問題が起きてしまった、じゃあどうやって解決しようか」などと取り組んでいく中で、通信やシステムの仕様に関して深く知れる楽しさがあるんです。
ーネットワークの奥にある仕組みや繋がりを深く掘れば掘るほど、身につく知識や新しい発見が尽きないということですかね。
そうですね。入社の動機に繋がった部分でもあるのですが、コニカミノルタ情報システムは、システム会社単体としては約200名規模の大きすぎない組織だからこそ、ネットワークに関わる幅広い業務に深く入り込めて、多彩な分野の専門性を高めていけるところが魅力だと思います。
例えば、大きいシステムに何か新しい仕組みを導入しようとする時、今まで知らなかったような仕様や壁に直面しますが、そうした難題に対して、周辺を巻き込みながら解決を図っていく、そこが今の仕事の面白いところです。思い悩むこともありますが、周りのメンバーが親身にアドバイスをしてくれるので助けられています。直接的な成果を実感できる環境と、成長をサポートしてくれる仲間がいること。それが、私が今もコニカミノルタ情報システムで働き続けている大きな理由ですね。

本音で話せるから課題の解像度が上がり、価値ある仕事を生む
ー “内販比率100%”が入社の決め手の一つでもあったということですが、逆にデメリットに感じることや、入社してみて改めて感じた良さはありますか?
デメリットでいうと、良くも悪くも顔馴染みの方たちと一緒に仕事するので、線引きが曖昧になる部分もあり、一次対応が出遅れたり、契約外のことをイレギュラーで対応して自分たちの首を絞めたり…といったことはあるかなと感じています。
それは良い意味で言えば、フレキシブルに対応できる強みと言えるかもしれませんが、いずれにしろ、関係性に甘んじず、自分の役割を個々できちんと判断して、何かトラブルがあれば迅速に動ける体制を整えることで、効率的で強固な組織作りをしていくことが大事だと思います。
ーその一方で、同じグループだからこそ本音で踏み込んで話ができるのは、大きなメリットやアドバンテージになりそうですね。外販だと、どこまで情報をオープンにして良いのかも見極めが難しくコミュニケーションの深度を深め辛いこともあると思います。
はい、仰る通りだと思います。お互いのインフラ環境やグループの戦略や指針を予め理解しているのは、非常に重要なポイントです。前提条件の認識の擦り合わせに時間を取られることなく、現状の課題についてじっくりと腹を割って話せるので、そこは大きなメリットだと感じます。
ー前提条件のキャッチアップができていないと、想定外の工数がかかったり予算が膨れ上がったりして問題になることもありますもんね。
そうですね。プロジェクトが頓挫する要因は、得てして本来は最上流でもっと詰めておかないといけなかった部分にあった、というのも多いですしね。知っておかないといけない前提条件を細かく理解できているからこそ純粋に課題解決にパワーを注げる、エンジニア冥利に尽きる環境だと思います。
ーちゃんと本来すべき仕事の価値に向き合えるというのは大きいですね。
ユーザーを深く知るため、現地に赴く時間も大事にしたい
ーネットワークインフラ周りですと、今はどんな案件が推進されているのですか?
私の部署では、今はリモートアクセスサービスのプロジェクトが動いています。社外から社内のイントラ内にあるシステムにアクセスできるものですが、現在導入中のサービスが間もなく終了するので、後継製品の選定や全体的な構成の見直しなどを進めているところです。
ー今後も恒常的に出社とリモートのハイブリットワークを進めていく環境を整えておられるんですね。セキュリティを担保しながら、外部からも場所を選ばずアクセスできて、どこでも仕事ができるような状態を作っていこうというところでしょうか。
そうですね。リモートか出社かを状況に応じて選択できて、どこでも仕事できる点は大きな魅力ですし、働く人の立場として、とても嬉しいところだなと思います。
ーIさんは、コニカミノルタ情報システムの中でも、出社頻度が高いエンジニアとお聞きしましたが、どういったお考えからなのでしょう?
現在では、週1日以上は出社するのが会社のルールになっています。私自身は、リモートと併用しつつも現地に赴くケースが割と多いです。
というのも、例えばネットワークの設置やリプレースの話が出た時、現地で得られる情報量と、モニター越しに入手する情報量は、なかなかの差があると感じているからです。自分の目で状況を見て吸収した方が飲み込みも早いですし、ユーザーと対面で話すことで、困っていること、実現したいことがより現実的な悩みとして具体的に伝わってくるように思うんですよね。
ですので、リモートワークも取り入れていますが、重要な場面だったり、現地に行く方がより情報を得られそうだったりする場合は、やはり現地に赴くことを大事にしています。
ーユーザー側も、課題を正確に言語化できるとは限りませんしね。リモートでのやりとりですと、ますますそういった言語化能力を求められるように思います。
そうですね。言葉で伝える難しさもそうですし、図解も交えながら画面越しに全てを説明するというのも、なかなか伝わり辛いところがあります。ネットワーク分野に詳しい方でしたらそこまでのすり合わせは不要かもしれませんが、不慣れだった場合はユーザー側の負荷が大きくなってしまうんですよね。
ーどこまでの知識があるのか、リアルにどんなことに困っているかを、最初に現地でキャッチアップできれば、後の工程がリモートで進む形になってもズレが起きにくいですね。
はい。やはり直接会ってコミュニケーションを一段深く行うことで、相手に負担のない形でリードしていけるように思いますし、後工程も円滑に進めていくことができると思います。

グループ全体に関わる大規模案件を手がけるPMへ
ーこれからの目標について教えてください。
コニカミノルタ情報システムは、コニカミノルタグループ内のITに関する困りごとを引き受け、問題解決を支援する役割を持ちます。閉じた環境にこもりすぎず、外部のベンダーやパートナーと連携し、最新技術情報のキャッチアップを怠らず、様々なニーズに対応できる存在になりたいです。
また、現在は中小規模の案件を担うケースが多いので、今後はグループ全体に関わるような大規模プロジェクトをマネージャーとして成し遂げたいと考えています。上流からプロジェクトを動かしていく上でも、常にユーザー目線を忘れないことを大事にして、実際にシステムを使うユーザの視点を重視した提案や運用を行えるよう努めていきたいです。
私が大切にしたいコニカミノルタのバリュー
Customer-centric
顧客の要望を把握したうえで、最適な提案を行うことが私たちの役割だと考えています。そのため、メールやチャットでのコミュニケーションにおいても、常に顧客の発言の“真意”を把握するように努めています。